「お金の勉強をしたいけど、何から始めればいいかわからない…」
そう感じている人におすすめなのが、FP3級(ファイナンシャル・プランニング技能検定)です。税金・保険・投資・年金など、社会に出てから必ず関わる知識を幅広く学べる国家資格で、初心者でも独学で十分合格を狙えます。
この記事では、私が大学生としてFP3級に独学で合格した実体験をもとに、勉強法や使用教材、試験当日の流れ、合格後に感じたことまで詳しく紹介します。
現在はCBT(コンピュータ)方式に完全移行しており、試験日を自由に選べるのも魅力。忙しい学生や社会人でも、1か月あれば合格レベルに到達可能です。
また、実技試験「資産設計提案業務」の内容や対策ポイント、つまずきやすい年金・税金分野の攻略法もわかりやすく解説します。
これからFP3級を受けようと思っている方にとって、最短で合格を目指すための具体的な道筋が見えるはずです。
FP3級を受けようと思った理由

私がFP3級を受けようと思った理由は、ただ一つ。お金の知識を身につけたかったからです。大学生になりアルバイトで収入を得るようになると、貯金や支出の管理、将来の生活設計について考える機会が増えました。しかし、学校では税金や保険、年金といった身近なお金の仕組みを体系的に学ぶことはほとんどありません。そのため、基礎から幅広く学べるFP3級は、自分にとって最適な資格だと感じました。
実際に勉強を始めてみると、税金の仕組み、保険の種類、年金制度、投資の基礎など、これまで曖昧だった内容がクリアになりました。知識を得たことで、自分の家計管理にも役立ち、将来の資産形成に対する不安も軽くなったと実感しています。
「就職や転職に役立つから」ではなく、純粋にお金のことを理解したいという思いから始めた勉強でしたが、その結果として就活や社会人生活にもプラスになると感じています。
FP3級の試験概要(簡単に解説)
FP3級(ファイナンシャル・プランニング技能検定)は、お金の基礎知識を幅広く学べる国家資格です。
投資・保険・年金・税金など、将来に直結する内容を体系的に理解できる点が大きな特徴です。
現在はすべて CBT方式(コンピュータ試験) に移行しており、誰でも気軽に受験できる環境が整っています。
試験日程(自分の都合で選べる)
FP3級は、以前のように年3回の実施ではなく、全国のCBT会場でほぼ通年受験が可能です。
受験したい日時と会場を自分で選んで予約するスタイルなので、学校や仕事のスケジュールに合わせて受けられます。
試験日が自由に選べるのは、忙しい大学生や社会人にとって大きなメリットです。
試験内容(学科+実技の2本立て)
試験は「学科試験」と「実技試験」の2つに分かれています。
- 学科試験:ライフプラン、リスク管理、金融資産運用、税金、不動産、相続・贈与の6分野
- 実技試験:私は「資産設計提案業務」を選択しました。ライフプランや投資、保険の見直しなど、実際の相談事例に基づく問題が中心です。
どちらも選択式で、CBT画面上でクリックして回答する形式。
紙のマークシート方式よりもスムーズで、時間配分もしやすい試験です。
合格率(約85%前後で初心者でも十分狙える)
FP3級の合格率は、学科・実技ともに85%前後。
内容は身近なテーマが多く、初学者でもしっかり勉強すれば十分に合格可能です。
特に「資産設計提案業務」は学んだ知識を実践的に使う内容なので、理解しながら学べる点が魅力。
FP3級の勉強法の流れ(体験談ベース)
私はFP3級の勉強を始めたのが試験の約1か月前でした。
勉強時間は1日1〜2時間ほど。アルバイトや授業の合間を使って、無理のないペースで進めました。
結果的に合計で約40〜50時間程度の学習で合格できました。短期間でも計画的に進めれば十分に間に合います。
インプット:参考書で全体像をつかむ
最初の1週間は、参考書をざっと読みながら全体の流れをつかむことを意識しました。
使用したのは「みんなが欲しかった!FPの教科書(TAC出版)」です。
この教材は図やイラストが多く、専門用語がかみ砕かれているので、初心者でも理解しやすいです。
特に最初は細かい暗記よりも、「FPの勉強でどんなことを扱うのか」をざっくり把握するのがポイントです。
アウトプット:問題集を繰り返して定着
インプットが終わったら、すぐに問題集でアウトプットに切り替えました。
使ったのは同シリーズの「みんなが欲しかった!FPの問題集」です。
最初は解けない問題も多かったですが、間違えた箇所に印をつけて繰り返し解くことで少しずつ理解が深まりました。
学科・実技ともに過去問の傾向が似ているため、過去問を解くことが最短ルートです。
私はスマホでFPの過去問アプリも併用し、通学中のスキマ時間に演習を行いました。
つまずいたポイント:年金と税金の範囲
苦戦したのは年金と税金の分野です。
国民年金・厚生年金の仕組みや所得控除の種類などは似た言葉が多く、最初は混乱しました。
そのため、表や図を使って整理したり、繰り返し同じ問題を解くことで理解を定着させました。
FP試験では暗記よりも「制度のつながり」を理解しておくことが重要です。
FP3級の試験当日の感想と結果

試験当日はCBT方式(パソコン試験)で受験しました。
会場では受付後に本人確認を済ませ、指定された席に着席します。
パソコン画面上で操作方法を確認してから試験が始まるので、初めてでも安心して受けられました。
他の受験者も静かに取り組んでおり、集中しやすい環境でした。
難しかったところ
最も難しく感じたのは年金と税金の分野です。
似た用語が多く、制度の違いを理解していないと混乱します。
特に「所得控除」や「公的年金控除」などは細かい条件が問われるため、表や図で整理して覚えることが大切です。
また、計算問題ではケアレスミスを防ぐために、見直し時間をしっかり確保するよう意識しました。
予想より簡単だったところ
一方で、ライフプランニングや金融資産運用の問題は解きやすく感じました。
過去問と似た形式が多く、事前に問題集を繰り返していたことで落ち着いて解答できました。
実技の「資産設計提案業務」も、数字の扱い方や問題の流れが練習した内容とほぼ同じで、過去問演習が最大の武器になりました。
合格通知を見たときの気持ち
試験が終わると、画面上にその場で点数と合否の目安が表示されます。
すぐに結果が見られるのはCBT試験の大きなメリットで、「努力がすぐ報われた」と感じました。
ただし、正式な合格通知(認定証)は後日、日本FP協会から郵送で届きます。
通知を受け取ったときは、改めて「本当に合格したんだ」と実感が湧きました。
これまで勉強してきた時間を思い出し、達成感とともに次のステップ(FP2級)への意欲が高まりました。
FP3級をこれから受ける人へのアドバイス
FP3級は、参考書と問題集の2冊があれば十分に合格を狙える資格です。
教材を増やしすぎると途中で挫折しやすくなるため、信頼できる1シリーズに絞って学習するのがおすすめです。
私は「みんなが欲しかった!FPの教科書」と「同シリーズの問題集」を使いましたが、内容が整理されており、独学でも理解しやすかったです。
勉強期間の目安は約1か月。
1日1〜2時間の学習を続ければ、十分に合格レベルに到達できます。
FP3級の範囲は広いですが、出題傾向は毎回似ており、繰り返し学ぶことで確実に得点力が上がる試験です。
短期間でも計画的に取り組めば、学生や社会人でも無理なく合格を目指せます。
また、勉強を始めたばかりの頃は「内容が難しそう」と感じる人も多いでしょう。
しかし、そんなときこそ「まず過去問から解いてみる」のが突破口になります。
最初はわからなくても、問題を通して出題のパターンや頻出テーマが見えてきます。
特にCBT試験では過去問と似た形式が多いため、実践的な練習が最も効果的な対策です。
FP3級は合格率が高いだけでなく、学んだ知識をそのまま生活や将来設計に生かせる資格です。
焦らずコツコツ進めれば、誰でも合格できる実用的な国家資格だと感じました。
記事全体のまとめ
FP3級は、お金の基礎知識をしっかり身につけたい人にとって最適なスタート資格です。
大学生や社会人1年目でも独学で十分に合格を目指せますし、実生活にも直結する学びが多いのが大きな魅力です。
私自身、FP3級を通して「お金の仕組みを理解する力」が身につき、お金に関してさらに興味を持つことができ、将来の資産形成やライフプランを考えるきっかけになりました。
試験勉強をきっかけに、自分のお金に向き合う意識が大きく変わったと感じています。
✅ 重要ポイントまとめ
- FP3級は完全CBT方式で、全国の会場から日時を自由に選んで受験可能
- 試験は「学科+実技(資産設計提案業務)」の2構成
- 合格率は約85%前後で、初心者でも十分狙える
- 勉強期間は1か月(1日1〜2時間)で合格レベルに到達可能
- 使用教材は参考書+問題集の2冊で十分
- 難しいと感じたら、まず過去問を解くことで理解が深まる
- 年金・税金の範囲は要重点対策。表や図で整理して覚えるのが効果的
- 試験直後に点数が表示され、合格通知は後日郵送で届く
- 学んだ知識は家計管理・投資・保険など、実生活でそのまま活かせる
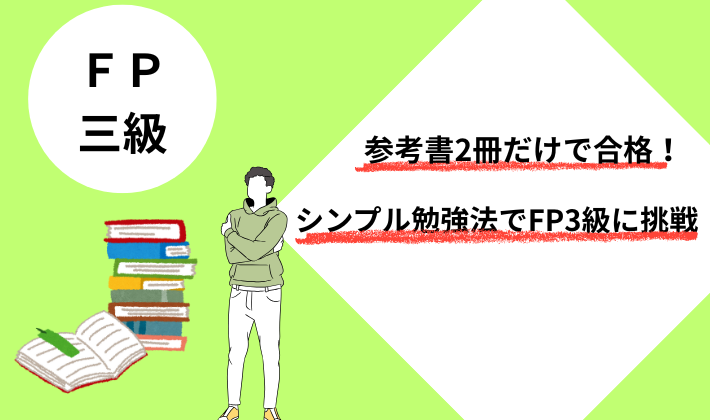
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d41e4d5.f923f903.4d41e4d6.af8de337/?me_id=1213310&item_id=21607085&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6012%2F9784300116012_1_17.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d41e4d5.f923f903.4d41e4d6.af8de337/?me_id=1213310&item_id=21607020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6050%2F9784300116050_1_17.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
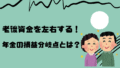
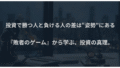
コメント