「年金は65歳からもらえるもの」――多くの人がそう思っていますが、実は年金は繰り上げて60歳から受け取ることも、繰り下げて75歳まで遅らせることも可能です。受け取り方ひとつで、一生の年金額に大きな差が生まれることをご存じでしょうか。例えば、早く受け取れば安心感はありますが、生涯にわたって減額が続きます。逆に、受け取りを遅らせれば毎月の年金額は増え、長寿であれば総額で大きな得につながります。このように重要なのは「損益分岐点」を理解し、自分の寿命やライフプランに合った判断をすることです。さらに、iDeCoや新NISAといった制度を組み合わせることで、節税と資産形成を同時に実現することも可能です。本記事では、繰り上げ・繰り下げの仕組みやメリット・デメリット、損益分岐点の考え方、そして老後資金戦略までをわかりやすく解説します。
年金制度の基本をわかりやすく解説
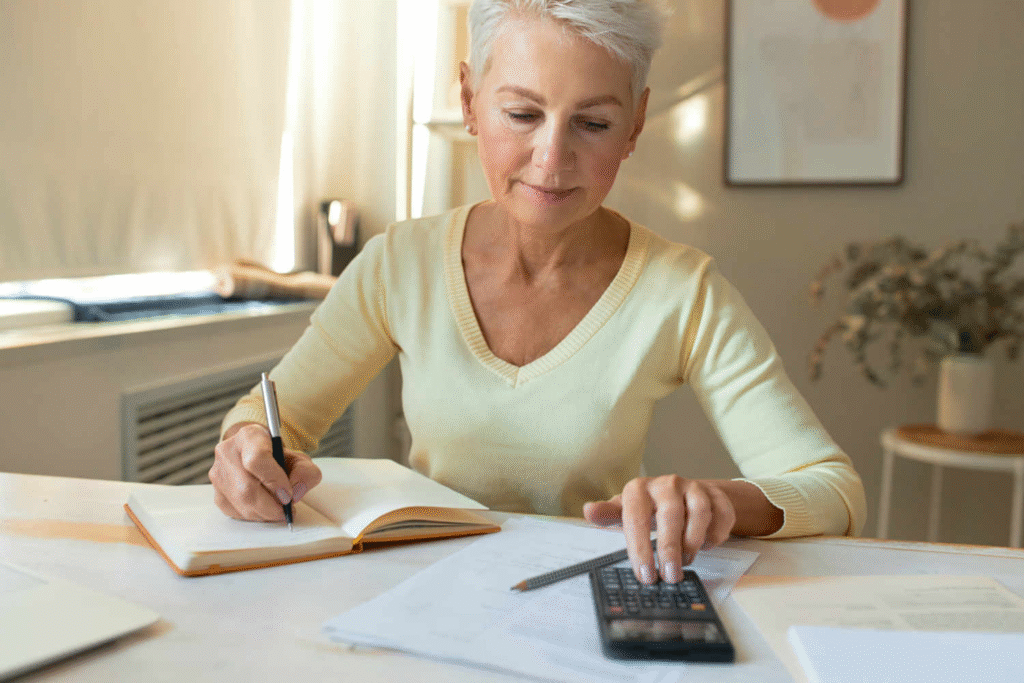
公的年金(基礎年金・厚生年金)の仕組み
日本の年金制度は「2階建て構造」になっています。
- 1階部分:国民年金(基礎年金)
20歳以上60歳未満のすべての人が加入。自営業やフリーランス、学生、専業主婦(第3号被保険者)も対象。保険料は全国一律で、2024年度は月16,980円。納付期間が40年で満額の老齢基礎年金を受給できます。 - 2階部分:厚生年金
会社員や公務員が対象。給与に応じて保険料が決まり、事業主と折半して負担。現役時代の収入や加入年数に比例して将来の受給額が変わる仕組みです。
つまり、自営業やフリーランスは1階建て、会社員や公務員は2階建ての仕組みを利用していることになります。
年金の受給開始年齢と標準的な受給額
年金の受給開始は原則65歳です。ただし、希望すれば60歳から繰り上げ受給、70歳まで繰り下げ受給も可能です。
- 老齢基礎年金:満額は年額約80万円(月額約6.6万円)。40年間(480か月)すべての期間で保険料を納めた人が対象。納付期間が短ければその分減額されます。
- 厚生年金:平均的な会社員で年額約170万円前後(月14万〜15万円)。収入が高く、加入期間が長い人ほど受給額も増える仕組みです。
また、受給開始を繰り上げると1か月につき0.4%減額され、繰り下げると1か月につき0.7%増額されます。つまり、60歳から早く受け取ると終生減額、70歳まで遅らせると終生増額になるため、ライフプランと寿命を踏まえた選択が必要です。
会社員・自営業・フリーランスの年金制度の違い
職業ごとに受け取れる年金額には大きな差があります。
- 会社員・公務員(第2号被保険者)
→ 基礎年金+厚生年金の2階建て。平均受給額は月15万〜16万円程度。企業によってはさらに企業年金や退職金が加わり、老後資金のベースは比較的安定しています。 - 自営業・フリーランス(第1号被保険者)
→ 基礎年金のみ。満額でも月約6万6,000円で、生活費としては不足しやすい。退職金制度もないため、自助努力による資産形成が欠かせません。 - 専業主婦(第3号被保険者)
→ 自分で保険料を払わなくても、配偶者の厚生年金に付随して基礎年金を受け取れる仕組み。将来的には月6万円程度が目安です。
このように、会社員と自営業では老後に受け取れる金額に約2倍以上の差が出るのが実態です。フリーランスや個人事業主は、公的年金だけに頼らず、iDeCoやNISAなど私的制度を組み合わせることが現実的な対策といえます。
繰り上げ支給とは?仕組みとメリット・デメリット

60歳から受け取れる繰り上げ支給の仕組み
年金の繰り上げ支給とは、本来65歳から受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金を、60歳から前倒しで受け取れる制度です。受給開始年齢を早めると、その分毎月の年金額は減額されますが、一生涯にわたり繰り上げた年齢から年金が支給されます。
制度上、1か月単位で繰り上げが可能であり、例えば61歳から、62歳からといった柔軟な選択ができます。高齢期の働き方や貯蓄額に応じて、早めに生活資金を確保したい人にとって選択肢となります。
繰り上げで減額される率と一生続く影響
繰り上げ受給を選ぶと、1か月につき0.4%ずつ年金額が減額されます。
たとえば、65歳からの受給額が月6万6,000円(基礎年金満額)の場合:
- 60歳から受給 → 5年(60か月)繰り上げ × 0.4%=24%減額 → 月約5万円
- 62歳から受給 → 3年(36か月)繰り上げ × 0.4%=14.4%減額 → 月約5万6,500円
一度減額された年金額は一生涯そのままで、途中で元の金額に戻ることはありません。そのため、寿命が長い人ほど総受給額は少なくなり、老後の資金計画に大きな影響を与えます。
早めに受給するメリットと向いている人の特徴
繰り上げ支給にはデメリットが目立ちますが、状況によってはメリットもあります。
メリット
- 60歳から受け取れるため、早期退職後の生活資金を確保できる
- 貯蓄が少ない人でも安心して生活費に充てられる
- 病気や寿命を考慮し「長くは受け取れない」と判断する場合に有効
繰り上げ支給が向いている人の特徴
- 健康に不安があり、長寿を前提としにくい人
- 貯蓄や退職金が少なく、早めに生活資金が必要な人
- 働かずに60歳以降すぐに年金に頼りたい人
一方で、長生きするほど繰り下げ受給の方が有利になるため、自身の健康状態やライフプランを冷静に見極めることが大切です。
繰り下げ受給とは?長く働く人に有利な制度
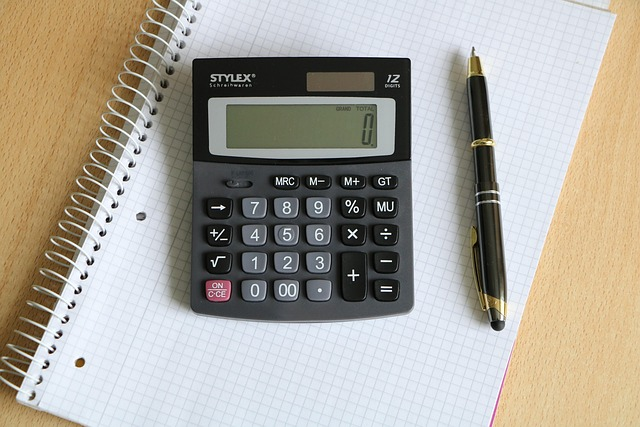
70歳まで繰り下げ可能な仕組み
公的年金は原則65歳から受け取りますが、受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」制度を使えば、最大で70歳からの受給が可能です。2022年の制度改正により、75歳まで繰り下げられるようになり、選択肢が広がりました。
繰り下げをすると、その遅らせた期間に応じて年金額が増額され、一度増えた年金額は一生涯減らないのが特徴です。長く働き続ける人や、他に収入源がある人にとって魅力的な選択肢といえます。
増額率と将来の受給額シミュレーション
繰り下げ受給では、1か月遅らせるごとに0.7%増額されます。
例えば老齢基礎年金(満額・年80万円)の場合:
- 65歳から → 年80万円(月約6.6万円)
- 70歳から → 60か月遅らせ × 0.7%=42%増 → 年113.6万円(月約9.4万円)
- 75歳から → 120か月遅らせ × 0.7%=84%増 → 年147.2万円(月約12.2万円)
このように、繰り下げ期間が長いほど受給額は大きく増え、長生きすればするほど総額で有利になります。
繰り下げ受給が有利になるケースと注意点
有利になるケース
- 70歳以降も働き続けて収入がある人
- 健康状態が良く、長寿を見込める人
- 年金以外に退職金や貯蓄などの生活資金が十分にある人
注意点
- 受給を遅らせている間は年金が一切支給されないため、生活資金の確保が必須です。
- 長生きしなかった場合は、総額では受給できる金額が少なくなる可能性があります。
- 税金や社会保険料の負担も増えるため、手取り額を考慮したシミュレーションが重要です。
損益分岐点を理解しよう

繰り上げ・繰り下げで変わる損益分岐点
年金の繰り上げ支給や繰り下げ受給を検討する際、重要なのが損益分岐点です。損益分岐点とは、「繰り上げ」「繰り下げ」と「65歳からの通常受給」で、どの年齢で総受給額が逆転するかを示すラインです。
例えば、老齢基礎年金満額を基準にした場合:
- 60歳から繰り上げ → 総額ではおおむね77〜78歳で65歳開始と逆転
- 70歳から繰り下げ → 総額では82〜83歳で65歳開始と逆転
つまり、寿命が損益分岐点より長ければ繰り下げが有利、短ければ繰り上げが有利となります。
平均寿命と受給開始年齢の関係
厚生労働省の統計によると、日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳(2023年時点)です。これを考えると、多くの人は損益分岐点を超える年齢まで生きる可能性が高く、繰り下げ受給の方が結果的に得をするケースが多いといえます。
ただし、健康状態や働き方、家族の状況によって実際の寿命や必要資金は異なるため、「平均寿命」だけで判断するのは危険です。自分自身のライフスタイルや持病の有無を踏まえた検討が必要になります。
ライフプラン別の損益分岐点シミュレーション
損益分岐点は、収入や生活状況によっても変わります。
ケース①:60歳で早期リタイアし、貯蓄が少ない人
→ 生活資金が必要なため、繰り上げ支給で早めに年金を確保する方が安心。
ケース②:65歳以降も働き収入がある人
→ 年金を遅らせても生活に困らないため、繰り下げ受給で将来の受給額を増やすのが有利。
ケース③:健康に不安があり長寿を見込みにくい人
→ 損益分岐点を超える前に亡くなる可能性があるため、繰り上げ受給の方が合理的。
ケース④:長寿家系で資産に余裕がある人
→ 繰り下げ受給で年金額を増やし、長期的に得をする選択が望ましい。
📊 繰り上げ・繰り下げ別の損益分岐点比較表(老齢基礎年金満額を例に試算)
| 受給開始年齢 | 年間受給額(概算) | 65歳開始と比較した増減 | 損益分岐点(逆転する年齢) |
|---|---|---|---|
| 60歳開始(繰り上げ) | 約56万円(▲30%) | 毎年▲24万円 | 77〜78歳 |
| 65歳開始(基準) | 約80万円 | ±0 | ― |
| 70歳開始(繰り下げ) | 約113.6万円(+42%) | 毎年+33.6万円 | 82〜83歳 |
| 75歳開始(繰り下げ最大) | 約147.2万円(+84%) | 毎年+67.2万円 | 86〜87歳 |
年金制度を賢く活用するための実践的なポイント

繰り上げと繰り下げを判断する基準
繰り上げや繰り下げを選ぶ際は、寿命予測・健康状態・就労状況・生活資金の余裕を軸に考えることが大切です。
- 60歳以降すぐに生活費が必要 → 繰り上げ支給が有利
- 65歳以降も働ける、もしくは十分な貯蓄がある → 繰り下げ受給で年金額を増やす方が得
- 損益分岐点を超えるかどうかが重要な判断材料
つまり、目先の資金ニーズと長期的な受給総額のバランスを見極めることが必要です。
iDeCoやNISAと組み合わせた老後資金戦略
年金だけに頼るのではなく、iDeCoや新NISAを活用した資産形成を組み合わせることで、老後資金のリスク分散が可能になります。
- iDeCo:掛金が全額所得控除となり、節税しながら老後資金を積み立てられる
- 新NISA:運用益が非課税で、流動性もあるため「中期資金+老後資金」の両方に活用できる
例えば、生活費の土台は公的年金で確保し、不足分をNISAやiDeCoの資産運用で補うハイブリッド戦略が有効です。
専門家に相談すべきタイミング
年金や投資の最適解は人それぞれ異なるため、迷ったときはファイナンシャルプランナー(FP)や年金相談窓口に相談するのがおすすめです。
- 定年退職を控えている時
- 繰り上げ・繰り下げを選択する前
- iDeCoやNISAを始める前に資金計画を立てたいとき
特に、年金と税金・社会保険料の関係は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで思わぬ損失を避けられます。
まとめ:年金制度を賢く活用するために
結論として、年金の繰り上げ・繰り下げ制度を正しく理解し、自分のライフプランに応じて選択することが老後の安心につながります。さらに、iDeCoやNISAを併用すれば、節税と資産形成を両立でき、年金だけに頼らない安定した生活基盤を築くことが可能です。
✅ 重要なポイントまとめ
- 年金は65歳開始が基本だが、繰り上げ(60歳から)・繰り下げ(最大75歳まで)が選べる
- 繰り上げ受給は早く受け取れるが減額が一生続き、損益分岐点は77〜78歳前後
- 繰り下げ受給は遅らせるほど増額され、長寿なら総額で有利になる(損益分岐点は82歳以降)
- 日本人の平均寿命(男性81歳・女性87歳)を考慮すると、繰り下げが得になるケースが多い
- ただし、生活資金の余裕・健康状態・就労状況によって最適解は変わる
- iDeCoは所得控除で節税しつつ老後資金を確保できる制度
- NISAは運用益非課税で流動性があり、中期資金と老後資金の両方に対応可能
- 公的年金を土台に、iDeCo・NISAを組み合わせたハイブリッド戦略が有効
- 判断に迷うときは、ファイナンシャルプランナーや年金相談窓口に相談するのが安全
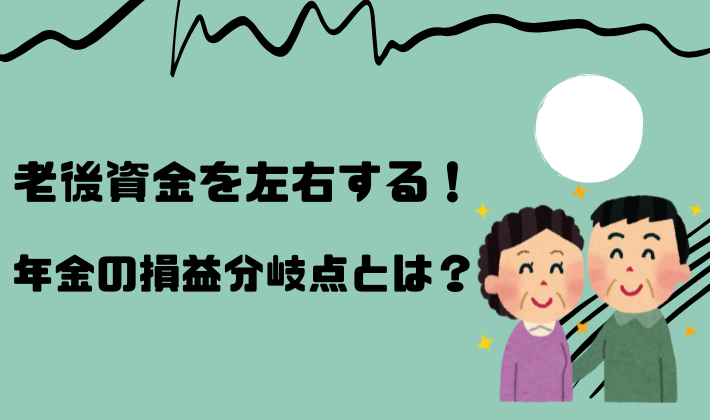

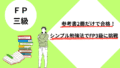
コメント