「お金の本なんて、社会人になってからでいいや」
そう思っていませんか?でも実は、大学生こそ“お金の知識”を身につける絶好のタイミングです。なぜなら、これからバイトや奨学金、仕送り、将来の就職や生活費など、「お金と関わる場面」が急に増えてくるから。
とはいえ、「何から学べばいいのか分からない」「難しそう」と感じる人も多いはず。
そこで今回は、“お金初心者の大学生”にも読みやすく、実生活にすぐ役立つ本を5冊厳選してご紹介します。
- 貯金や節約の基本が物語で学べる本
- 図解で読みやすい家計や投資の教科書
- これからの働き方やお金の常識がわかる教養本
どれも実際に読んで「これは読んでよかった!」と感じたものばかり。
この記事を読めば、難しい数式も専門用語も不要で、“使えるお金の知識”が自然と身につきます。
あなたも今日から、将来に差がつく「お金の教養」を始めてみませんか?
なぜ大学生こそ「お金の本」を読むべきなのか?

社会に出る前に知っておきたい“お金の常識”とは
「お金の勉強って、社会人になってからでいいんじゃない?」
そう思っている大学生は少なくありません。けれど実際には、社会に出る前の大学生こそ、お金の常識を身につけておくべきです。
例えば、家賃・保険・税金・ローン・投資といったワードは、すべて将来の生活に関わります。にもかかわらず、学校ではこうした実践的なお金の知識を教わる機会はほぼありません。
だからこそ、まずは「お金の本」を通じて、
- 収入と支出のバランス
- 貯金と投資の違い
- 生活にかかるリアルなお金の感覚
をつかんでおくことが、将来の“金欠”や“お金の失敗”を防ぐ第一歩になります。
お金に強い人は早くから“金融リテラシー”を磨いている
金融リテラシーとは、「お金の知識と正しい判断力」のこと。
この力がある人は、無駄遣いをせず、収入に応じた生活ができ、お金を「貯める・守る・増やす」判断が自然にできるようになります。
実際、お金に強い人の多くは、学生のうちからお金についての本を読んだり、小さな投資や節約を始めたりと、早くから“行動”しています。
「大人になったら自然とわかるもの」と思っていると、気づいたときには
- 給料は入るけど毎月ギリギリ
- クレカの支払いが不安
- 投資ってなんだか怖い…
という状態に。
だからこそ、学生のうちに正しい知識を得ておくことが「将来のお金に強くなる下地」になるのです。
大学生のうちに読むことで将来差がつく理由
同じ大学生でも、「お金の知識を持っている人」と「そうでない人」では、将来の選択肢に大きな差が出ます。
たとえば、
- 奨学金の返済計画が立てられる
- 就職後すぐに家計管理ができる
- つみたてNISAやiDeCoなど制度を早く活用できる
といったことが、人生設計をラクにしてくれます。
そして何より、「お金に振り回されない人生」を選ぶ力が身につきます。
お金は、ただの道具。けれどその使い方ひとつで、自由にも不安にもなるもの。
だからこそ、大学生の今こそが“お金の勉強のベストタイミング”なんです。
実際に読んでよかった!初心者の自分でもわかりやすかった「お金の本」5選
① バビロンの大富豪の教え|貯金と複利の原則を学ぶ名著
古代バビロニアの物語を通じて、「お金を増やす7つの知恵」が語られる名著。
この本の魅力は、シンプルだけど本質的な“お金の原則”を物語形式で学べることです。
特に印象的なのが「収入の1割を必ず貯金する」という考え方。
これは後に学ぶ「複利の効果」や「資産形成」にもつながります。
文章も難しくなく、お金の基礎に触れたい人の入門書として非常におすすめです。
「まず1冊読むならこれ!」という声が多いのも納得の1冊。
② お金の大学|お金の使い方・守り方を図解でやさしく学べる
YouTubeチャンネル「リベ大」で有名な両学長による、お金の教科書。
貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う、の5つの力を図解でわかりやすく解説しています。
特に「固定費の見直し」「投資の基礎」など、すぐに実践できる知識が豊富で、家計管理や節約にも役立つ内容が詰まっています。
学生のうちから、「自分で選ぶ力」「お金の判断力」を育てたい人にぴったり。
カラー&図解メインなので、読書が苦手な人にもおすすめです。
③ 金持ち父さん 貧乏父さん|“稼ぐ力”の本質を知る入口に
「学校はお金の稼ぎ方を教えてくれない」――この問題提起から始まるロバート・キヨサキのベストセラー。
収入には「労働収入」と「資産収入」があることや、お金に働かせる考え方など、学生のうちに知っておくべき価値観が詰まっています。
内容自体は少し抽象的なところもありますが、「働き方」や「人生観」に気づきをくれる一冊。
「将来お金持ちになりたいけど、どうしたらいいか分からない」人に刺さる本です。
④ 13歳からの金融入門|経済のしくみを知りたい学生に最適
日経新聞が編集した中高生向けの一冊。とはいえ、大学生にも非常に役立つ“教養としてのお金の本”です。
税金、年金、金融政策、投資など、難しそうに見えるテーマも、やさしい言葉とイラストで丁寧に解説されています。
特に「なぜ働いても税金が引かれるのか」「国の借金ってなに?」といった、ニュースで聞くけど理解しづらいテーマがクリアになります。
経済に苦手意識がある人の最初の一歩として、非常におすすめ。
⑤ LIFE SHIFT|人生100年時代に必要なお金と働き方の考え方
少し難易度は高めですが、「人生100年時代」と言われる今、大学生にもぜひ読んでほしい一冊です。
この本では、「教育→就職→定年退職」という古いモデルが通用しなくなる時代に、どのようにお金と時間を使うべきかが語られています。
金融資産だけでなく、「スキル・人脈・健康」も資産と考える視点は、就活やキャリア形成にも直結する内容です。
将来を見据えて「長く幸せに生きる力」を育てたい人に、ぴったりの教養本です。
本を読んだあとの「実践」がカギ!大学生におすすめの行動ステップ
読んだだけで終わらせない「お金習慣」の始め方
お金の本を読んで「なるほど!」と思っても、実生活で行動に移さなければ、知識はすぐに忘れてしまいます。
重要なのは、読んだあとに“どんな小さな一歩でもいいから行動すること”です。
たとえば、
- 財布の中身を見直して支出の傾向をつかむ
- 今日から“収入の10%を先取りで貯金する”習慣をつける
- 自分のお金の悩みを紙に書き出してみる
こうした行動だけでも、知識が“自分ごと”として定着しやすくなります。
特に学生は、収入も支出もシンプルだからこそ、「お金の習慣化」の練習に絶好のタイミングです。
家計簿アプリや投資シミュレーションで実践してみよう
読書で知識を得たら、次はデジタルツールで“見える化”することがカギです。
具体的には、以下のようなアプリやサービスがおすすめです。
✅ 家計簿アプリ(Zaim、マネーフォワード MEなど)
→ スマホで手軽に収支を記録でき、無駄遣いの「見える化」ができます。自動連携機能も便利。
✅ 投資シミュレーション(楽天証券、SBI証券などの無料ツール)
→ 「毎月1万円を年利5%で積み立てたら?」というような、将来のお金の増え方が体感できます。
✅ 生活費の予算を表にする(GoogleスプレッドシートでもOK)
→ 月々の支出目安を設定し、実際の数字と比べて改善点を発見できます。
こういった「実際に触れて、動かす」体験は、読んだ知識を行動と結びつけて定着させるために非常に効果的です。
NISA・つみたて投資・副業など、次のアクション例を紹介
もう一歩踏み出したい人には、行動に直結する「選択肢」を知っておくのも大切です。
✅ つみたてNISA(新NISA)
→ 月1万円からでもOK。インデックスファンドなどで「資産運用」の入り口に。将来の複利効果が期待できる。
✅ iDeCo(個人型確定拠出年金)
→ 節税しながら老後資金を準備できる制度。ただし、20歳以上・就業条件ありなので要確認。
✅ 副業・スキル活用(クラウドワークス、note、フリマアプリなど)
→ 「お金を増やす力」を小さくでも育てていく練習になります。
重要なのは、「完璧に始めること」ではなく、できる範囲から“今”動き出すこと。
最初は不安でも、学んだことを1つでも行動に移せば、お金に対する自信と行動力が育っていきます。
まとめ|「知る」だけじゃなく「動く」ことが未来を変える
お金についての知識は、早く学べば学ぶほど将来に大きな差がつきます。
今回ご紹介した書籍は、どれも初心者でも読みやすく、行動につなげやすい内容ばかり。
ですが、いちばん大切なのは――“読んで終わり”にしないことです。
✅ 本記事の重要ポイントまとめ
- 大学生こそお金の本を読むべき理由
→ 社会に出る前に、基本の「稼ぐ・貯める・使う・増やす・守る」を知ることが、未来の安心につながる。 - 実際に読んでよかった初心者向けお金の本5選
→ 図解・物語形式・教養型など、読みやすくてためになる本ばかり。まずは1冊選んで読むだけでOK。 - 行動に移すことが“知識を生きた力”に変えるカギ
→ 家計簿アプリやシミュレーション、NISAの情報収集など、小さな実践から始めると定着しやすい。
たとえ今、お金に詳しくなくても大丈夫。
「知ろうとしたこと」「学ぼうとしたこと」その一歩が、確実に未来を変えていきます。
このブログをきっかけに、あなたの“お金との付き合い方”が変わり始めたら嬉しいです✨
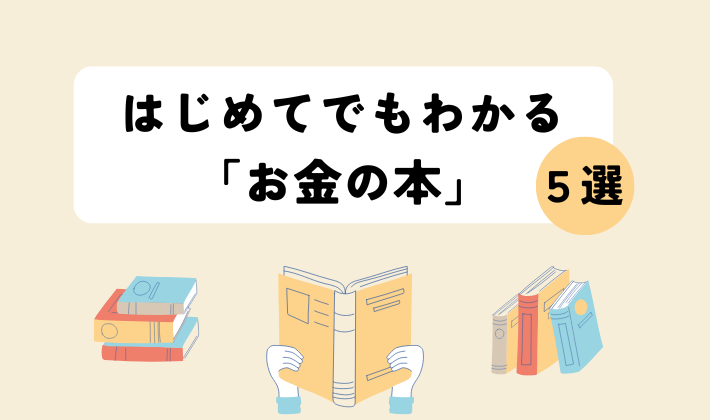

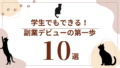
コメント